まずは安全確保をしよう
生活を整えることが防災につながります。「難しそう」と身構えずに日常的にできることから少しずつ
始めていきましょう。
屋外の場合
●地下にいたらすぐに地上に出る
●上から物が落ちてこない場所に逃げる
●施設や交通機関では職員の指示に従う
屋内の場合
●わざわざ火を消しに行かない
●風呂やトイレなど閉じ込められる可能性がある場所には行かない
●スーパー安全地帯に逃げる

家族が離れた場所にいる場合は?
家族用のLINEグループを活用する
LINEは災害時に役立つアプリ!大規模な災害が発生すると、「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」という無料Wi-Fiが開放されます。このサービスを利用し、LINEグループで家族と連絡を取り、自分の現在地を伝えるとよいでしょう。

家族で決めた “待ち合わせ場所”に集合
被災時、家族が一緒にいるとは限りません。そんなときに大切なのは、学校・近所の公園・広域避難所など、どこに集合するのかあらかじめ決めておくこと。待ち合わせ場所の中でも具体的な目印を決めておくとスムーズに集合できます。

【CHECK!】子どものお迎えは家族みんなが行けるようにしておこう!
幼稚園・保育園のお迎えが必要になる場合もあるので、先生の名前や保育室の場所、お迎えの手順はママ・パパだけでなく、祖父母など家族全員で共有しておこう。
安全なところに避難しよう
非常階段を利用しよう
電気が途絶えるとエレベーターは使用できなくなります。高階層に住んでいる場合は普段から非常階段で子どもと一緒に上り下りする練習をして非常時に備えましょう。

避難が必要か見極める
焦って家から飛び出すのは危険!道路が割れていたり、がれきが落ちていたりする場合もあるので、揺れがおさまってから家の中と外、どちらが安全か見極めて避難してください。
避難場所へ移動する
家族がバラバラの場所で被災した場合、家族で決めた“待ち合わせ場所”に避難しましょう。そのためにも普段から避難経路を散歩がてらに下見しておくことが大切です。

車輪があるものはNG
道路がでこぼこしていると、車輪のあるものは危ないので、徒歩での移動が基本。抱っこして避難するときは、子どもの両手足が飛び出さないように、スリングを使いましょう。
教えてくれたのは…
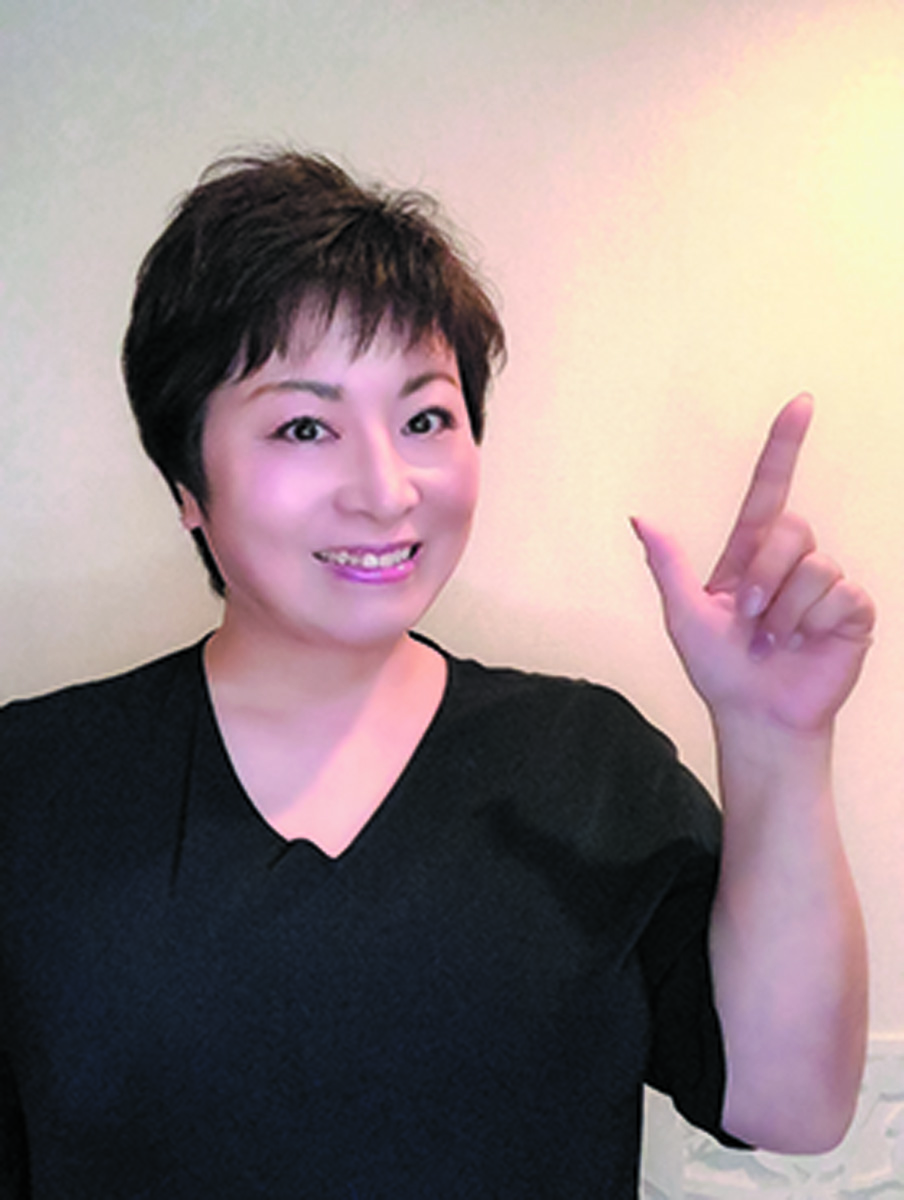
国際災害レスキューナース、
一般社団法人育母塾 代表理事
辻 直美 さん
国際災害レスキューナースとして、東日本大震災や熊本地震など、国内外30カ所以上の被災地で医療支援を行う。近年は講演や防災教育にも注力。また、身も心も包む「まぁるい抱っこ」を提唱し、大切な命を守る術を伝えている。
辻 直美さんから 「ひとこと」
最大の防災は、近所の人に挨拶をしたり、笑顔で接したりと日常で“ええかんじの人”になること。普段からコミュニケーションを取っておくと、いざというときに周りと助け合いながら困難を乗り越えることができます!

いかがでしたか?参考になりましたか?
他の関連記事はコチラ↓↓
子どもを守る!防災スタートガイド|家庭でできる地震対策の基本


















